物流コストの新基準、「市場価格」から「適正原価」へ
2020年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に対して、運賃水準を約8%引き上げた「標準的運賃」が告示されてから1年が経過しました。
昨年2024年に告示された標準的運賃は、運賃水準を引き上げただけではなく、燃料高騰分や高速道路料金、荷待ち・荷役などの輸送サービス以外の対価について水準を設定、さらには下請けに発注する際の手数料(10%)を導入し、適正に価格転嫁できるようにしたものです。
この見直しの背景としては、荷主に対して、原価高騰および運送業務において発生する役務に対して「適正な」運賃・料金を収受できること、多重下請け構造の是正等がありました。
- 【関連するコンサルティング】
- ≫「物流コスト妥当性評価」の詳細はこちら
目次
標準的運賃の課題と値上げラッシュによる影響
告示当初は、標準的運賃と「市場価格」の乖離が大きく運送事業者も標準的運賃を使用し、荷主に対して価格交渉、見積もり提示をすることは現実的ではありませんでした。しかしながら輸送力不足の歯止めの兆しがなく、法改正による規制や効率化推進の強化を進めつつ、トラックドライバーの雇用の確保、賃上げの原資となる適正運賃の改善も進めなければならない状況となりました。
2024年問題、物効法施行による物流面の規制が強化される一方、適正運賃収受、つまり、運賃値上げの向かい風となったのが、様々な品目による値上げラッシュです。
2025年4月から食品主要企業における値上げは4,000品目超となりました。4月末時点の2025年通年の累計値上げ品目数は14,409品目となり、すでに前年実績を上回っています。値上げによる在庫滞留、消費低下による買い控えの結果、荷動きの鈍化が続くと運賃交渉が難航することが想定されます。
≫ 関連資料「今さら聞けない標準的運賃のしくみ、どこまでの値上げを許容すべき?」をダウンロードする(無料)
適正運賃収受に向けた法改正の動き
社会情勢の変化がありながらも、日本国内の重要なインフラである物流を維持・継続するためには「適正な」運賃を収受する動きを止めてはなりません。
これまでに告示された標準的運賃には法的拘束力はなく、運送事業者が荷主に対して適切な価格交渉を進めることができるよう国が水準を定めたものでした。これに対して、今国会で成立を目指す貨物自動車運送事業法の一部改正案の概要が公表されています。
改正案の一つとして、今後は標準的運賃を廃止し、国が「適正原価」を設定し、「適正原価」を下回る運賃は法令違反となる内容です。これによりトラック運送業の規制、つまり適切な取引環境が実現すると考えられています。これまでの「いかに安い運賃で運べるか」というマネーゲームから脱却し、価格交渉が適切に進むことになる一方で、荷主にとっては大幅なコストアップにつながります。
しかし短期的な視点でコスト増加に目を向けるのではなく、適正な運賃が持続可能な物流体制の構築につながり、結果としてサプライチェーン全体の安定化に貢献するという長期的な視点を持つことが重要です。
さいごに
物流業界全体における課題解決に向けた取り組みとして、「運賃の値上げ」避けられませんが、これらの物流業界の動きを踏まえたうえで、自社の物流戦略をどうあるべきか改めて再構築するタイミングがきています。
この法改正へ向けた動きをきっかけに自社の物流戦略を見直してみてはいかがでしょうか。
参考資料:「帝国データバンク 価格改定動向調査」
【関連コンサルティング】物流コスト妥当性評価
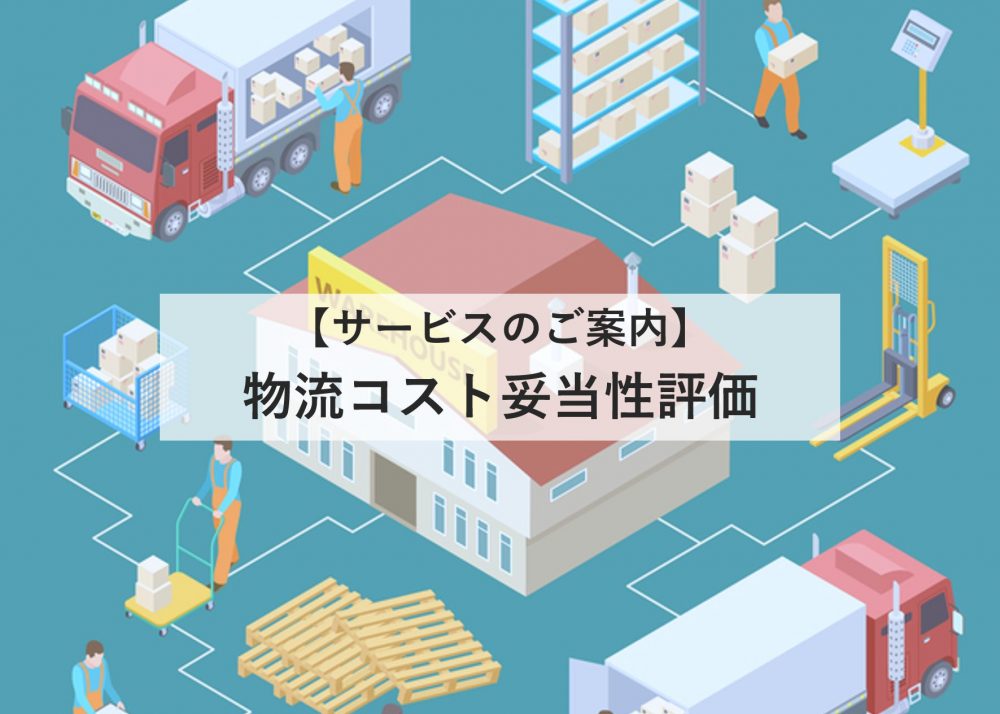
自社物流コストが妥当なのか定量的に把握できていますか?流業界の最前線でコンサル支援を行ってきた船井総研ロジが独自のデータベースを活用し、貴社の物流コストの妥当性を明らかにいたします。
【物流コスト妥当性評価の特徴】
・業界水準との比較
・物流コストの定量・定性評価
・実行・改善策のご提案
【関連ダウンロード資料】今さら聞けない標準的運賃のしくみ、どこまでの値上げを許容すべき?
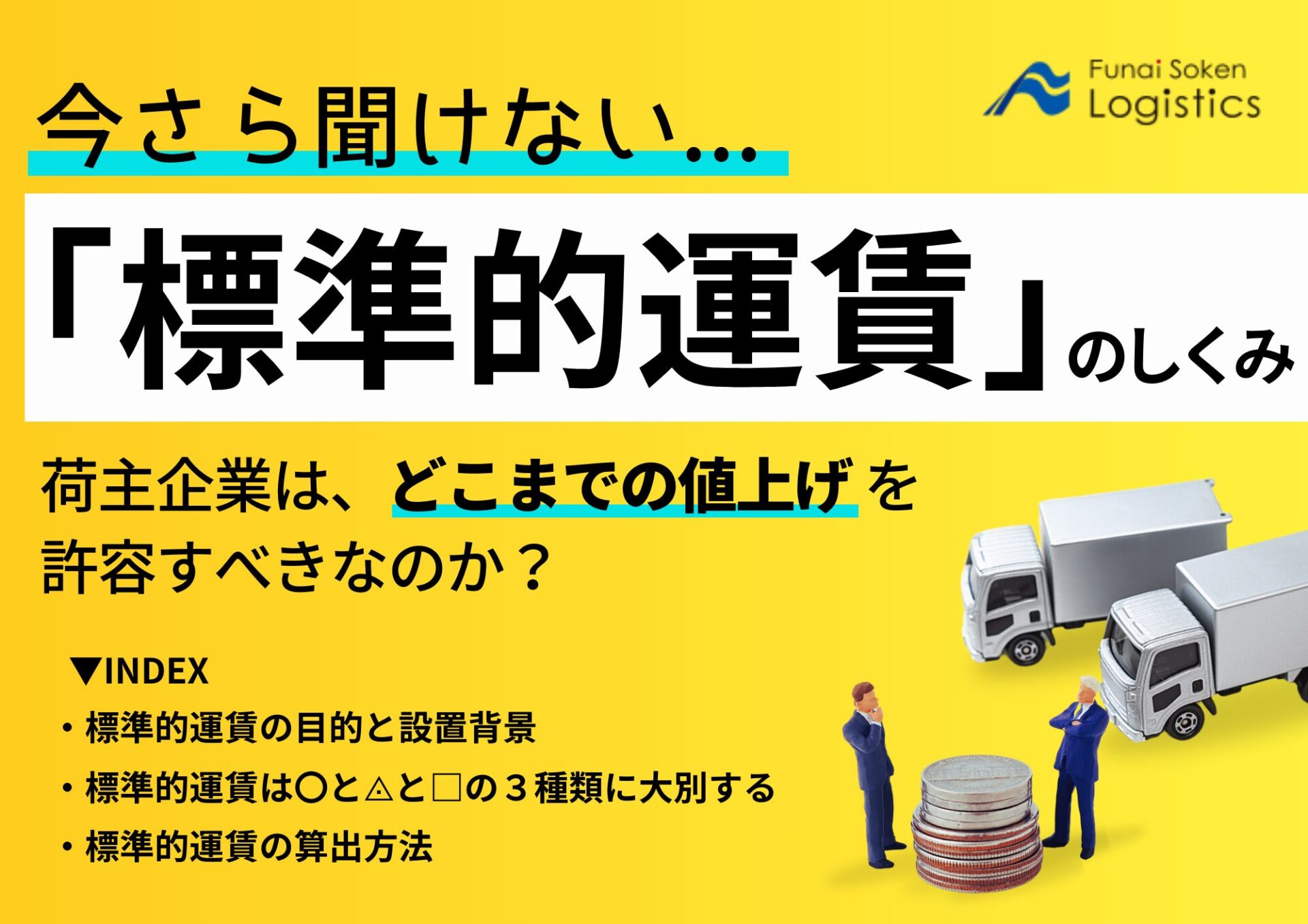
本コンテンツでは、標準的運賃設置の目的や適正運賃の算出方法、物流企業との運賃交渉の際にどこまで値上げを許容すべきか、具体的なポイントをくわしく解説します。
【物流コスト妥当性評価の特徴】
・標準的運賃の目的と設置背景
・標準的運賃は〇と◬と□の3種類に大別する
・標準的運賃の算出方法






