実践!物流コスト妥当性評価~あるべき単価を現実へ~
前回のコラム(物流コスト適正化の第一歩!物流コスト妥当性評価のススメ)では、物流コスト妥当性評価の重要な観点の一つとして、持続可能な事業運営が可能となる「あるべき単価」について定義しました。
今回は、この定義を具体的な実施段階に落とし込み、どのように考え、「あるべき単価」を設定すべきかをお伝えします。
- 【関連するコンサルティング】物流コスト妥当性評価
- ≫「物流コスト妥当性評価」の資料請求はこちら(無料)
目次
「あるべき単価」を現実的なラインに落とし込むための現状分析
机の上で理想的な「あるべき単価」を算出したとしても、それが実際の相場感(標準的運賃など)や自社の物流業務に合致していなければなりません。物流コストの妥当性評価を絵に描いた餅で終わらせないためには、現場の視点と具体的なアクションプランが不可欠です。
まず「あるべき単価」を現実的なラインに落とし込むためには、自社の物流実態を正確に把握することから始めます。
1.現状分析
どのような貨物を、どのくらいの頻度で、どこからどこへ輸送しているのか?
保管スペースはどの程度利用しているのか?
どのような荷役作業が発生しているのか?
物量データを定量的に把握することが第一歩です。
▶ 現状把握の必要視点
・輸送: 貨物の種類、輸送頻度(日/週/月)、輸送量(個数、重量など)
・ルート: 発着地、各ルートの輸送量(便数、積載率など)
・ 保管: スペース利用状況(面積、容積など)、保管貨物の種類と量(アイテム数、保管期間など)
・荷役: 作業内容、発生頻度(回数、時間など)、使用設備
▶ 現状把握の方法例
・物流実態のデータ分析: 輸送品目、量、頻度、発着地状況、保管状況、荷役内容などを実績データに基づいて確認
・物流現場視察: 倉庫内の保管状況、荷役作業の様子などを視察し、ボトルネックや改善点を目視で把握
・ヒアリング:事前に実施した物流実態のデータ分析と物流現場視察の結果を踏まえ、データや現場で確認された事象について、その詳細な状況、背景、運用実態を確認し、より多角的に物流の実態を把握。
2.コスト分析
各物流運営にかかる人件費、燃料費、資材費、設備費などを市況情報から料金項目別に細かく洗い出します。間接部門のコストも考慮に入れる必要があります。
▶ 物流運営費用の項目例
・輸配送費:ドライバー人件費、燃料費、車両維持費、高速道路料金など
・倉庫・保管費:入出庫作業員人件費、倉庫賃料、光熱費、梱包資材費など
・荷役・流通加工費:作業員人件費、流通加工用資材費、設備維持費など
・間接部門費:物流管理者人件費、システム運用費、オフィス関連費など
上記分析項目にて自社の物流オペレーションにおける「コスト構造」が明確になり、「あるべき単価」をより現実的に設定するための土台となります。
さいごに
物流料金単価の妥当性評価は、自社の物流オペレーションを正確に理解し、最適なパートナーシップを築き、競争力を高めるための重要なプロセスです。
当社では、物流コストの妥当性を評価し、適正なコスト管理を実現するためのサービスを提供しています。現状のコストが適正かどうかを客観的に分析し、無駄の削減やコスト最適化のための具体的な改善策をご提案します。値上げの妥当性やその影響についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
【関連コンサルティング】物流コスト妥当性評価
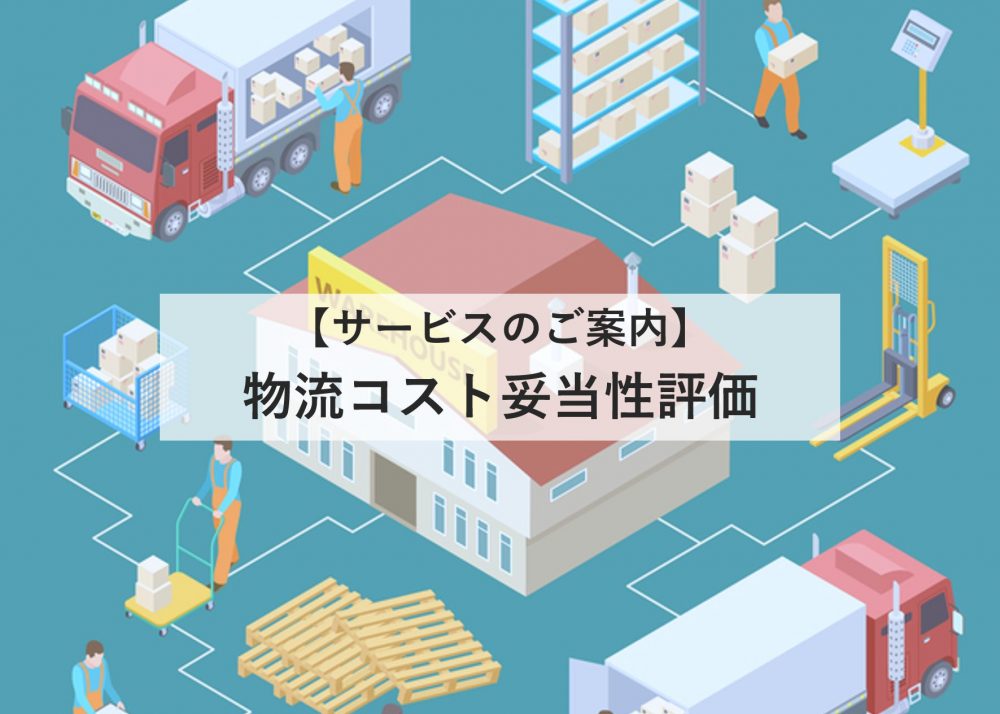
自社物流コストが妥当なのか定量的に把握できていますか?流業界の最前線でコンサル支援を行ってきた船井総研ロジが独自のデータベースを活用し、貴社の物流コストの妥当性を明らかにいたします。
【物流コスト妥当性評価の特徴】
・業界水準との比較
・物流コストの定量・定性評価
・実行・改善策のご提案






