運賃交渉、どう対応すればいい?独占禁止法抵触リスクを踏まえた荷主企業の対策ポイント
2023年11月29日に公正取引委員会は、下請け取引において、「労務費(会社が従業員に支払う給料)の上昇分を適切に価格に転嫁するための指針」を策定・公表しました。
それに伴い、荷主企業は運送会社との運賃交渉において、独占禁止法に抵触することなく、持続可能な物流体制を構築していく必要があります。
今回は、運賃交渉において荷主企業が留意すべき対策について解説いたします。
目次
運賃値上げが求められる理由
運送業界では、物価高騰と法改正という二つの側面から、運賃値上げが不可避となっています。
1.輸送コストの増加
人件費(特にドライバーの人件費)は運送原価において最も高い割合を占めていますが、最低賃金は年々上昇傾向にあります。また、燃料費も高騰しており、運賃上昇に大きな影響を与えています。
2.規制への対応
2024年4月からの時間外労働上限規制は、ドライバーの労働時間短縮とそれに伴う輸送能力の低下を招き、既存の運賃体系では運送会社の事業継続が困難となります。荷主企業としては、安定的な物流を維持するために法規制に対応した適正な運賃での契約が不可欠となります。
独占禁止法抵触リスク
公正取引委員会より、コスト上昇分の価格転嫁について、価格交渉の場で十分な協議を行わずに価格を据え置いたり、価格引上げの要請に対して書面などで回答せずに価格を据え置いたりする行為は、「優越的地位の濫用」にあたる可能性があるとされています。
以下は、独占禁止法抵触リスクのある行為の具体例です。
① 一方的な価格決定:運送会社と交渉の場を設けずに、一方的に価格を 提示(決定)する行為。
② 値上げ交渉の拒否:運送会社から値上げの申し入れがあったにも関わらず、正当な理由なく交渉を拒否する行為。
③ 荷待ち時間の料金未払い:運送会社が強いられている荷待ち発生対する料金未払い。
④ 値上げを理由とした取引停止:値上げを要求してきた運送会社との取引を、一方的に停止するような行為。
荷主企業に求められる対策
運送業界の構造的な変化と法規制への対応を踏まえ、荷主企業には以下のような取り組みが求められます。
① 定期的な協議の場の設定:運送会社と定期的にコミュニケーションを取り、価格交渉を行う場を設定する必要があります。
② 物流コストの可視化と分析:過去の運賃推移、重量、距離、作業内容などを考慮し、総合的に運賃の妥当性を判断します。過去の運賃推移や費目別の分析を通して、物流コスト構造を把握する必要があります。
③ 取引の透明性確保:値上げ根拠を明確化し、輸送費と付帯作業料の内訳を区別します。荷役作業等の内容と料金を明確化し、配送条件の見直しを検討します。
さいごに
運賃交渉においては、独占禁止法に抵触しないよう運送会社との信頼関係を構築し、労務費上昇分 の適切な転嫁を促すため 定期的なコミュニケーションと公正な価格交渉の実施が重要です。
船井総研ロジでは、荷主企業の物流体制におけるリスクを評価し、具体的なフィードバックを行うサービス、「物流リスク診断」がございます。
上記のような問題を抱えられている企業はぜひご検討ください。
【関連サービス】物流リスク診断
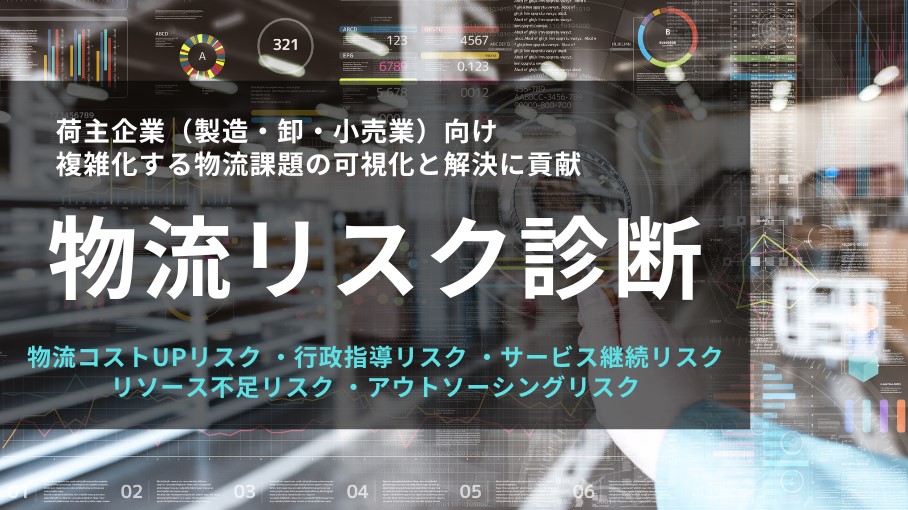
「物流リスク診断」では、貴社が保有する物流リスクをすべて洗い出し、具体的な対応策と、取り組むべき優先順位を明確にします。
【物流リスク診断の特徴・強み】
・現行物流体制の課題の抽出
・物流リスクへの対応策の提案
・物流戦略再構築の方向性






