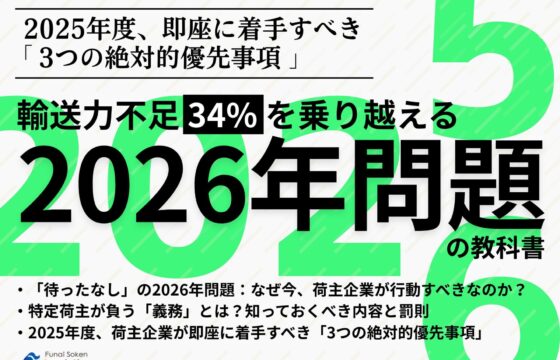その物流、時代遅れになっていませんか?未来を勝ち抜くための「物流体制の再構築」
本コラムでは、昨今の物流の変革期、ビジネスに求められる物流機能の役割の変化において、「DX・自動化」「物流フロー・ネットワークの最適化」を切り口とした未来を勝ち抜くための「物流体制の構築」に必要な3つの視点についてご紹介しますさせて頂きます。
昨今の「物流2024年問題」「物流効率化法」に象徴されるような、今、日本の物流は大きな変革の岐路に立たされています。 かつては「コストセンター」と見なされ、コスト削減ばかり追求されていた物流部門に対し、顧客ニーズの多様化、テクノロジーの進化、そして深刻化する人手不足といった外部環境の激変により、その役割は根本から見直されようとしています。
従来の改善活動の延長では対応が困難な今、事業の根幹を支える「物流体制の再構築」が急務です。
目次
▼なぜ今、「再構築」が必要なのか?
ビジネス環境の変化が、物流に新たな役割を求めています。
・多様化する顧客ニーズ:
当日配送、送料無料、個別対応など、物流が顧客満足度を左右する重要な要素となります。
・深刻化する労働力不足:
ドライバーや倉庫作業員の不足が深刻化し、従来の労働集約的なモデルが限界にきております。
・テクノロジーの急速な進化:
AI、IoT、ロボティクスといった技術が、物流のあり方を根本から変える可能性を秘めております。
・高まるサステナビリティへの要請:
脱炭素化や循環型経済への対応など、SDGs への取り組みや、ESG 経営をはじめ、環境・社会へ の配慮が企業の評価軸となりつつあります。
これらの変化は、物流を単なる「機能」から、企業の競争力を生み出す「戦略的基盤」へ進化しています。
▼未来を勝ち抜く物流体制へ。再構築の 3 つの視点
これからの物流体制の構築には、以下の 3 つの視点が欠かせません。
・デジタル化・自動化による「省人化と標準化」
WMS(倉庫管理システム)や TMS(輸配送管理システム)の導入はもちろん、AI による需要予測、ロボットによる庫内作業の自動化など、テクノロジーを活用し、人に依存しないオペレーションを構築します。これにより、生産性が向上するだけでなく、業務品質の平準化も実現できます。
・顧客体験を最大化する「価値創造物流」
物流を「コスト」ではなく、顧客体験を高めるための「投資」と捉え直します。緻密な在庫管理による欠品防止、柔軟な配送オプションの提供、丁寧な梱包など、物流品質の向上が、ブランド価値そのものを高めます。
・変化にしなやかに対応する「ネットワークの最適化」
BCP の観点から、特定の拠点や輸送網に依存するリスクを分散させると同時に、データ分析に基づいて、需要変動に合わせた最適な拠点配置や輸送モードを見直します。これにより、効率性と強靭性を両立したサプライチェーンを構築します。
弊社が主催する荷主企業の物流責任者向け勉強会「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン(LLS)」では、隔月に 1 回荷主企業同士の交流会に加え、先進的なお取組みをされている企業様や行政の方による講演を聴講することができます。値上げ対応やコストの見える化等における他社の動向や事例収集の場に適したコンテンツとなっております。みなさまのご参加をお待ちしております。
【関連サービス】荷主企業 物流責任者のための交流組織|ロジスティクス・リーダーシップ・サロン(LLS)

全国各地から荷主企業(製造業・卸売業・小売業)の物流責任者が集まる会員制の勉強会です。
アットホームな集まりで活発な議論や知識共有・知見の幅を広げることで、サスティナブルなロジスティクス体制の構築を実現することを目的にしています。
ご興味をお持ちいただきました方は、是非お試し参加(初回のみ無料)をお待ちしております。