法令対応できていますか?物効法に対応した輸配送スキーム改善
2026年4月に施行される改正物流総合効率化法(以下、改正物効法)は、2024年問題等による物流業界全体の輸送キャパシティ低下を背景に施行されます。改正物効法の施行は、単なる「効率化の推奨」から荷主と物流事業者の双方に具体的な責任を課すものとなりました。
改正物効法が突きつける課題の核心は、「物流におけるムダをなくし、業界全体の生産性を向上させること」です。その解決策の一つとして、輸配送スキームの最適化が挙げられます。
今回は荷主企業が輸配送スキーム最適化に向けたポイントと得られるメリットについて説明します。
- 【関連するダウンロード資料】
- ≫「『勝てる物流』を創造する戦略的ロードマップ」のダウンロードはこちら(無料)
目次
現状を打破する輸配送スキーム改善のポイント
1.配送回数・便数の合理性を定期的に検証する
物量は常に変化していくため、定期的に各輸配送先ごとに輸送物量を算出し、現状を見える化する必要があります。現状把握の上で、現行の配送回数や便数が適切であるか、検証していきましょう。
2.輸配送条件の見直し
輸配送条件があることによって、非効率なスキームにならないよう見直す必要があります。各拠点の条件(到着時間・付帯作業等)が運送会社やドライバーの負担になっていないか、現行スキームにおけるボトルネックとなっていないか等の観点から、現状把握することが重要です。
3.輸配送ルートの見直し
現行スキームにおいて、各配送先へ効率的なルートで輸配送できているかを検証する必要があります。ムダな遠回りや往復がある場合、ドライバーの拘束時間増加やコスト増加の要因となっている可能性があります。
上記3つのポイントを押さえ、輸配送スキームを見直し、改善することで、ドライバーの拘束時間や荷役作業の削減、積載率向上、コスト削減等のメリットが得られます。これらの取り組みは、改正物効法への対応策として有用であり、運送会社から選ばれる荷主となるための重要な施策となります。
≫ 関連資料「『勝てる物流』を創造する戦略的ロードマップ」のダウンロードはこちら(無料)
さいごに
物効法改正は、荷主企業の皆様にとって、自社の物流を根本から見直す絶好の機会です。この機会に、貴社の輸配送スキームの最適化改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。
【関連資料】「勝てる物流」を創造する戦略的ロードマップ
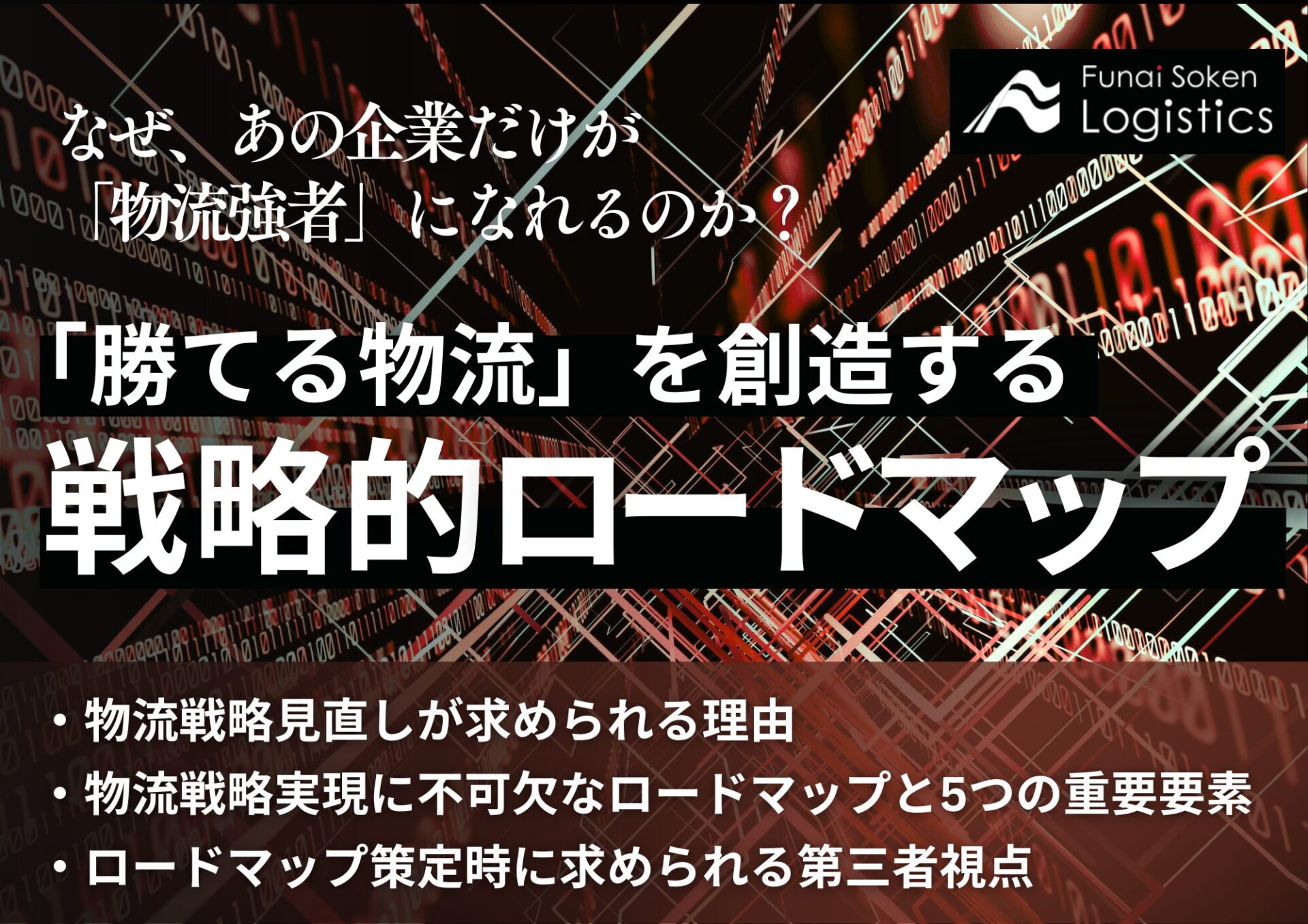
本資料では、物流戦略を「単なる目標」で終わらせず、「実行可能な計画」へと昇華させる「ロードマップ」に焦点を当て、その重要要素(最終目標、施策、スケジュール、KPI、担当、リソース)を体系的に網羅し、その意義と実践的適用について解説。
【この動画でわかること】
・物流戦略見直しが求められる理由
・物流戦略実現に不可欠なロードマップと5つの重要要素
・ロードマップ策定時に求められる第三者視点






